洋 舞
上野茂
(ナゴヤ劇場ジャーナル編集長)
2024年も、東海地区の洋舞公演はBALLET・NEXT「INNOCENT GRAY Day of Tears」(1月6日〜7日・名古屋市芸術創造センター)からスタートした。映画「エレファントマン」のモデルになったジョーゼフ・メリックの凄惨な物語。3度目の再演になるが、見る度に心を揺さぶられる、奇才・市川透の力作である。あなたは重度の皮膚病に侵された人物を正視できるのか—。醜悪な外見に覆われた知性や人間性を見極めることができるのか—。舞台の奥から客席に向け放たれた強い照明に、そう問われた気がした。3公演トリプルキャストで、私が観劇した初日は、主人公を長友麻衣花、彼女を支え続ける医師を梶田眞嗣が演じた。

(撮影・テス大阪)
当地の現代舞踊界をリードする倉知可英が、志を同じくするダンサーらを迎え「ナゴヤ・ダンス・シーンvol.10」(4月20日・千種文化小劇場)を開いた(以下、NDS)。発表の場の少ないダンサーたちのために、過去9回にわたり倉知のスタジオで行ってきたNDSの集大成にして最終回である。倉知は全国的にも有名なヒップホップダンサーKOUと共演。生命の誕生〜成長を幻想的に描いた。現代舞踊とコンテンポラリーの魅力を兼ね備えた斬新な公演だった。
岐阜県に拠点を置く舞踊団だが、傑出した創作作品とダンス力で全国的に高い評価を得る「かやの木芸術舞踊学園」にも触れておきたい。同団は3月に東京で開催された「第81回全国舞踊コンクール」の現代舞踊、群舞、児童舞踊の3部門で第1位を獲得。参加した8作品すべてが入賞、入選する快挙を成し遂げた。7月に開催された「第28回舞踊公演」(7月14日・土岐市文化プラザ)では、その8作品が披露された。オリンピック体操選手並みのダンステクニックを備えたジュニア、シニアのダンサーたち、人間愛に満ちた作品群。その圧巻のステージに幾度も胸が熱くなった。
現代舞踊協会中部支部の「ダンスパラダイス」(9月16日・千種文化小劇場)では、新人4組を含む14組がオリジナリティーを競った。新人グループは、いずれも高い身体能力を発揮。一般グループでは服部由香里が彼岸花を題材に作舞、13人のダンサーが心象的な群舞を繰り広げた「Impression〜おもいのりんのひがんばな」が興味を引いた。圧倒的なダンス力、構成、振付で群を抜いたのが苅谷夏の自作自演作「赤と黒のアダージョ」だ。あまりにドラマチックで情感のこもったダンスだった。メンタルとテクニックが合致すると、ダンス芸術はここまで昇華する—。それを実感した名舞台だった。

(撮影・水谷友也)
暮れには三代舞踊団が「第34回クリスマス定期公演」(12月22日・名古屋市青少年文化センターアートピアホール)でジャズダンスの本領を発揮。松岡伶子バレエ団が「騎兵隊の休息」、「ライモンダ」、創作「Labo」の「トリプル・ビル」(12月8日・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール)を公演。越智インターナショナルバレエは恒例の「くるみ割り人形」(12月26日・日本特殊陶業市民会館フォレストホール)を公演した。
洋 舞
小島祐未子(編集者・ライター)
少年王者舘の天野天街が7月に他界。しかし劇団員は直後の「それいゆ」4都市ツアーを完走した。「それいゆ」(仏語で太陽、ひまわりの意)の題名のごとく、天野の重要な主題〈生と死〉が放射状に飛び散るような感覚に襲われる同作は、帰還中の少年兵とその家族を軸に、二度の原爆投下、慎太郎と裕次郎の兄弟、猛獣に二度噛まれた松島トモ子など昭和の歴史・風俗史が絡み合って展開。それらを「ふたつの太陽」と見立てる趣向が面白い。半面、天野の怒りや悲しみ、やるせなさが強くうかがえて胸が塞がれる。生まれてきたのに必ず死を迎える命の不条理。「それいゆ」は眩しくて見えなくて闇に近づく現象を表現した作品だが、闇=死と同様、人間の生の輝きも星々に比べれば一瞬でしかないと思い知らされる。

(7月11日〜14日七ツ寺共同スタジオ)(撮影:羽鳥直志)
ささしまスタジオ主催「オイスターズがささしまライブの公園でつくる野外劇」は果敢な作品だった。作・演出の平塚直隆たちが立ち向かったのはビルや道路に囲まれた街なか。周辺は人の往来が可能で、野外劇というより市街劇の様相だった。使用条件の都合で音響はなく、俳優は地声で会話を繰り広げ、歌でも盛り上げる。360度回転式の客席も人力で動かしており、ギリシャ劇に通じるような演劇の原点が随所に見られた。題材の「ドラゴンクエスト」も親しみやすく、企画全体が演劇と地域、双方の活性化に新たな方法を示した。

( 9月17日〜23日ささしまライブ内1号公園)
「夫婦パラダイス〜街の灯はそこに〜」は北村想がシス・カンパニーに書き下ろした一種の商業演劇だが、実験性と大衆性が絶妙で興奮した。織田作之助の「夫婦善哉」をモチーフに、尾上松也と瀧内公美が主人公の男女を演じる舞台では現実と幻想が交錯。一筋縄ではない芝居ながら、北村と旧知の間柄の寺十吾の演出も冴え、客席は終始好反応。終幕は拍手喝采だった。作り手に信念があれば複雑な味わいの作品にも観客は応えてくれると改めて実感できたのは収穫だ。
子どものための舞台作品「ひかりとかげ」、音楽劇「マハルコ組曲」は劇場のアクセシビリティを巡る課題にも対応していた。「ひかりとかげ」はメニコン シアターAoiの芸術監督・山口茜による新作。科学実験や観客参加の要素を取り入れた舞台に子どもたちは大喜びだった。一方、春日井出身・中島弘象の原案著書「フィリピンパブ嬢の社会学」を舞台化した「マハルコ組曲」は、東京を拠点に活動する有田あんの脚本・演出ではあるが、公演は名古屋のみで当地の俳優も出演。フィリピン人の観客も多数来場し、涙していた。子ども、子育て世代、在日外国人など、劇場に足を運び難い人も演劇体験ができる場は今後も必要だろう。
2024年3月に行われた公開審査にて16号室/room16の八代将弥a.k.a.SABOが若手演出家コンクール2023最優秀賞に輝いた。受賞作「演出家コンクール最優秀賞受賞予定作品」は稽古風景を題材にした虚実ない交ぜの世界で観る者を驚かせた。また上演自体は2023年だが、廃墟文藝部の斜田章大が「4047(ヨンゼロヨンナナ)」で11月に発表された第30回劇作家協会新人戯曲賞を受賞。次世代のエースたちが確実に評価を高めた。
洋 楽
早川立大
(音楽ジャーナリスト)
三井住友海上しらかわホールが2月末で、30年にわたる音楽専用ホールとしての役割を終え、閉館した。会社の経営上の都合によるもので、音響抜群のここを本拠に活動していた地元音楽家たちの惜別コンサートが相次いだ。その中では、福本泰之ら教授陣の指揮で活力あふれる演奏を繰り広げた愛知県立芸術大学の弦楽合奏第18回定期演奏会(1月17日)、ピアニスト北村朋幹が初めて指揮を兼ね、モーツァルトやラヴェルのピアノ協奏曲を見事に弾き振りした名古屋フィルハーモニー交響楽団(以下、名フィル)のしらかわエクスプレス第4回「北村朋幹の世界」(2月9日)を挙げておく。

(12月5日宗次ホール)
[器楽]名古屋に本拠を置く3つのオーケストラの活動が目覚ましい。名フィルは名誉音楽監督の小泉和裕が室内楽的なモーツァルトのディヴェルティメントK.334と大編成のチャイコフスキーの交響曲第4番を振り分けた第526回定期公演(9月13日〜14日、愛知県芸術劇場コンサートホール)、セントラル愛知響では名誉音楽監督レオシュ・スワロフスキー指揮によるスメタナの連作交響詩「わが祖国」全曲の第205回定期公演(7月12日、同)、愛知室内オーケストラでは大家ゲルハルト・オピッツを独奏者に得たブラームスの大作ピアノ協奏曲第1番と第2番の特別演奏会(12月4日、同)がいずれもずば抜けた出来栄えだった。
アンサンブルでは、この地方で活動する男性メンバーだけで結成された弦楽合奏団「Union“無頼派”」の旗揚げ公演が、カルウォーヴィチの弦楽セレナードなど珍しい作品を取り上げて話題となった(10月17日、電気文化会館ザ・コンサートホール)。逆に、名古屋音楽ペンクラブ賞の受賞者たちが出演してきた「音環」演奏会が10回目の今回でひとまず一区切りとなったのは寂しい(9月26日、同)。
室内楽集団レーベインムジークは進行中のシューマンの室内楽作品全曲演奏会の第5回から第7回までをこなし(3月10日、7月6日、12月24日、同)、ピアニスト石川馨栄子はラヴェルのピアノソロ作品を2回の演奏会で弾き切った(4月6日、9月28日、同)。両者とも高水準の出来だった。
能 楽
飯塚恵理人
(椙山女学園大学教授)
2024年は名古屋能楽堂が4月から10月まで改修工事で閉館、やや寂しい一年であった。そんな中でも印象に残った舞台をいくつか紹介する。
1月21日名古屋能楽堂で、金春流による「日本全国能楽キャラバン名古屋公演」が行われた。金春穂高の《嵐山 白頭 働キ入リ》は、特に後ジテの蔵王権現がどっしりとした風格がありながら身体の切れがよく、ハタラキなど見ごたえがあった。後ツレの金春飛翔と金春嘉織の相舞もよく息が合っており、各人の日頃の修練の成果が遺憾なく発揮された。二曲目は《船弁慶 遊女ノ舞 替ノ出》。本田芳樹は前シテ静御前の序之舞が良く、後ジテ平知盛の霊は大将らしい風格を感じさせた。

(提供:公社金春円満井会、撮影:国東薫)
第29回「名古屋片山能」(3月9日、名古屋能楽堂)は片山伸吾の《巻絹》。片山のシテは神託を告げる巫女らしい威厳があり、神楽舞も美しかった。二曲目は片山九郎右衛門の《西行桜》。シテ謡は抑えた調子ながら口跡よく内省的で老木の桜の精に似つかわしかった。舞も典雅で美しく、春の夜遊の趣があった。
名古屋能楽堂の再オープンは11月2日の「やっとかめ文化祭DOORS」であった。狂言はやまかわさとみ氏作の《冥加さらえ》。井上松次郎、鹿島俊裕、今枝郁雄の三人が陽気な妖怪をおおらかに演じた。能はやはりやまかわさとみ氏の新作能《草薙神剣》。柏山聡子は大自然の力の象徴である八岐大蛇を切れの良い舞で表現した。衣斐愛は、特にミヤズヒメとして舞う場面に神話の姫らしい上品さがあって良かった。

(撮影:工房円)
11月3日「第45回名古屋金春会」(名古屋能楽堂)は金春穂高の《竹生島》。特に後ジテが龍神らしい迫力にあふれていた。本田布由樹の《清経 恋ノ音取》。シテを呼びだす竹市学の笛が素晴らしく、朧なシテの姿が徐々にくっきりと見えてくる様を感じさせた。
11月17日の名古屋宝生会「雪待能」(名古屋能楽堂)は衣斐正宜の《楊貴妃 玉簾》。飯冨雅介は、いつもながらワキの位を保ちつつ口跡の良さに謹厳な雰囲気があって良かった。衣斐正宜は、優美な中に仙界での孤独がにじむ楊貴妃を好演した。

(撮影:工房円)
二曲目は和久荘太郎の《女郎花》。こちらは風雅な雰囲気の前シテと地獄の責めを受けて苦しむ後ジテを上手に演じ分けていて好感が持てた。
名古屋能楽堂休館中、狂言共同社は栄能楽堂で「さかえ狂言御洒落会」を4月から10月までの毎月一回開催した。演目も《蝸牛》《瓜盗人》のようなポピュラーなものに加えて、《文蔵》《二千石》などの「語り芸」が主眼の狂言もあり、意欲的であった。若手の井上蒼大もしっかり舞台を勤め、狂言共同社の更なる発展が期待できる一連の公演であった。
また名古屋市文化基金事業「なごや子どものための巡回劇場 狂言がやってきた」も健在で、8月20日の天白文化小劇場、8月22日の守山文化小劇場、それぞれ質の高い狂言を提供したことも述べておきたい。
邦楽・邦舞
北島徹也
(CBCテレビ 調査役・金沢大学共同研究員)
西川流家元 西川千雅は今年も岡谷鋼機名古屋公会堂(名古屋市公会堂)で3回目の『名古屋をどりNEO傾奇者』(10/19、20)を開催、「名古屋ハイカラ華劇團」と題して、戦前戦後の二世鯉三郎の軌跡を重ねた。一方で今年は古典舞踊の会である『名古屋をどりCLASSIC』(3/23、24 御園座)も催し、〝日本舞踊も〟のエンタメ、〝日本舞踊を〟の古典という、西川流の両輪を見せた。千雅はまさ子、陽子と「雪月花」を舞い、鯉絵ほか「三社祭」と寿女司「傀儡師」、真乃女と京志郎「時雨西行」も印象に残る。西川流では前年春と秋に二つの表彰を得た真乃女がその記念公演として『しのじょ会華真』(4/14 日本特殊陶業市民会館(以下、市民会館)ビレッジホール)を催し、「三曲糸の調」と創作「蜻蛉比翼」で古典と創作の力量を発揮した。また、京志郎が新たに主宰となって「菊水会」(11/24 御園座)を催し「文屋」を踊った。亡き菊次郎へのよき追善である。

「三社祭」(左から)西川貴美子、鯉粧、鯉絵
ほか「三社祭」と寿女司「傀儡師」、真乃女と京志郎「時雨西行」も印象に残る。西川流では前年春と秋に二つの表彰を得た真乃女がその記念公演として『しのじょ会華真』(4/14 日本特殊陶業市民会館(以下、市民会館)ビレッジホール)を催し、「三曲糸の調」と創作「蜻蛉比翼」で古典と創作の力量を発揮した。また、京志郎が新たに主宰となって「菊水会」(11/24 御園座)を催し「文屋」を踊った。亡き菊次郎へのよき追善である。
名古屋演劇ペンクラブ賞の記念公演『五條園美リサイタル』(3/18 名古屋能楽堂)で、園美が主宰する、流派・ジャンルを超えた芸能集団 創の会の作品から「夢の光芒−平家物語より−」と、荻江節「八島」、ともに平家物語にちなんだ演目を披露し、さらに「続平家物語小品集」(12/14、15 名古屋能楽堂けい古室)では、創の会メンバーが立ち替わり駅伝のような奮闘を見せた。
「桜に舞う!〜舞踊とともに〜」(4/7 宗次ホール)で花柳朱実は、ショパンの「革命のエチュード」などをクラシックで見せ、名取55周年記念「朱ざくら會 朱実とひととき」(6/13 名東文化小劇場)で熟達の「藤娘」を舞った。「梅奈香会」(4/21 市民会館ビレッジホール)では「越後獅子」など子どもの活躍がみられ、花柳梅奈香は「鐘」で執念を、「助六」で侠客の闊達を表現した。
赤堀加鶴繪は『赤堀会』(5/26 市民会館ビレッジホール)で、創作「舞甘露」を豪奢に演じ、平安絵巻のような「華」を端正に舞った。
名残りが惜しまれるのは、舞納めに襟を正さしめるような「北州」での、工藤扇弥の舞台引退。『工藤会』(11/3 御園座)である。倉鍵は創作「天狐と蛇姫」でベリーダンスとの共演、寿々弥の更科姫と「紅葉狩」を出した。
稲垣舞比は山路遊子と「寒山拾得」を『豊美会』(7/21 市民会館ビレッジホール)で出し枯淡の境地を、友紀子は「おせん」の粋を表現した。
『内田会』(10/12 市民会館ビレッジホール)で、有美は家元の静かな気迫が備わった「廓八景」、寿子は粉雪の風情の「雪まんじ」だった。『明珠会』(2/23 名古屋能楽堂)での、山村楽乃『八島官女』は前半の牧歌風と後半のけなげさの対比が妙味である。『芸術鑑賞会』(9/23 市民会館ビレッジホール)で瑞鳳澄依は「天下る傾城」という古い変化所作事の一部を出した努力が佳い。「第41回芝流 芝の会」(11/2 御園座)で千桜こと西川牟喜幸は「神田祭」を京志郎と情趣たっぷりに。
今後期待したいのは、「舞初会」(4/20 昭和文化小劇場)での、結noKAIというグループで、稲垣舞比、内田有美、工藤彩夏、五條美佳園、西川古祐、花柳磐優、結月櫻が選曲、振付、演出まで話し合った作品「春夏秋冬〜結び、繋げる」に至る活動である。
長唄は、杵屋勝桃・勝千華『桃華の会』(5/19 天白文化小劇場)、杵屋見音代・見佳『見音代会』(6/1 八勝館)、杵屋六秋・六春『おやこ会』(11/9 今池ガスホール)などが催されたが、杵屋三太郎『杵三会』(11/24 日泰寺普門閣)では、三太郎襲名20年となることから歴代の三太郎とその門弟、関係者の追善法要も併せて行われ、また、三太郎は令和6年度名古屋市芸術奨励賞を受賞した。
名古屋市民芸術祭の伝統芸能部門で邦楽からは、「絃衣の会 佐藤亜衣 箏・三絃リサイタル」(11/14 電気文化会館ザ・コンサートホール)が特別賞となった。

「北州」工藤扇弥
美 術
安井海洋
(十九世紀書物史研究 美術批評)
2024年には二人の中堅世代の作家が息を吹き返したかのような活躍を見せた。彼らが死に体だったと言うのではない。歩一歩と積み重ねてきたものが、今年になってブレイクスルーに達したのだ。復活者の清新さで、二人の作品は筆者の目に飛び込んできた。鈴木雅明と山田純嗣の二人のうち、鈴木についてはTEZUKAYAMA GALLERYが発行した個展の記録冊子への寄稿文で記したので割愛する。
山田純嗣は2023年まで文化庁の研修制度でフィンランドのユヴァスキュラに滞在し、銅版画家の石山直司より独自のドライポイント技法の教授を受けた。ドライポイントの特徴はニードルで銅版を直刻し、その際に生じる小さな「まくれ」を利用して線の周囲に滲みをつくりだす点にある。しかし石山のドライポイント技法は極細のニードルを使用するため、まくれが肉眼ではほとんど認識できず、かつ彫刻に時間がかかる。
これまで山田は名画を再現した立体を撮影し、インタリオ技法で大画面に転写するシリーズを展開してきた。しかし海外研修を契機に、今までとは打って変わった正統派の銅版画を発表する。AIN SOPH DISPATCHのグループ展「I want to see the other side of the scenery you saw」で公開した新作は、過去の大作に比べるとずっと小さく、一日に数センチ四方ずつ彫り進めていくのだという。描かれるのは雪のユヴァスキュラの森である。さきにこの技法ではまくれが肉眼でほとんど見えないと述べた。だが掌におさまる小さな画面のなかの、降り積もった雪の表面が冷たい微風にふるえるさまや、白樺の表皮のゆらめきは、たしかに眼に触れている。見るのではなく眼で触れるというのが正しい極小の毛羽立ちに、自然物の精巧さに接したときに似た胸のふるえをおぼえた。
名古屋市美術館の「生誕130年記念 北川民次展」は、コレクションの柱である北川の作品を館外からも借用し、その事績を網羅した点で、同館による研究の集大成だといえる。メキシコ壁画運動のリアリズムに影響を受けた画風で想起されることの多い北川だが、全生涯の作品を通覧すると、時代ごとのムーブメントを積極的に取り入れる柔軟さと貪欲さを持っていたことがわかる。後半に示されたこどもたちの教育者としての側面も見逃しがたい。

ISO-HAAPASAARI JYVÄSKYLÄ,
FINLAND, OCTOBER(2024年)
愛知県美術館の「アブソリュート・チェアーズ 現代美術のなかの椅子なるもの」は、さまざまな形で現代美術に摂取された椅子の作品を提示することで、椅子と、腰かける私たちの身体について問いかける企画だった。ところで、本展には「障害と政治」という裏のテーマが見え隠れする。ダラ・バーンバウムの映像《座らされた不安》における自閉症者を連想させる常同行動を椅子の上で繰り返す女性の姿や、東大全共闘時の安田講堂内にいた渡辺眸が撮った写真集《東大全共闘 1968-1969》におけるバリケードにされた椅子、女性たちが議論する場で腰かけている椅子は、着座以外の使途や、対話の媒介としての役割など、椅子の多面性を示している。椅子は学校の教室のように人の行動を制約することもあれば、制約からの解放をもたらすこともあるのである。

(7月18日〜9月23日愛知県美術館)(撮影:城戸保)
文 学
清水良典
(文芸評論家・愛知淑徳大学名誉教授)
この地域に限らず地方の文化状況は年々地盤沈下が進んでいる。不景気を背景に有名な書店の閉店が相次ぎ、新聞や雑誌など紙のメディアも衰退の一途をたどっている。しかしこれはあくまで紙メディアを見た観測であり、ネット情報はいよいよ複雑巨大化し、SNSが社会コミュニケーションの中核となっている。あらゆる表現文化はそのような情報メディアの変化にアップデートできるか否かで、存続の命脈が決まるといってもいい。もろにその影響が顕れているのが文学である。
ここでは若い世代の実例として、1995年名古屋市生まれの現在大活躍中の作家、人間六度を紹介しよう。大学生のときに発症した白血病から立ち直った彼は、21年に「スター・シェイカー」(ハヤカワ文庫)でハヤカワSFコンテスト大賞を、同年「きみは雪をみることができない」(メディアワークス文庫)で電撃小説大賞メディアワークス文庫賞を受賞し、昨年は短編集『推しはまだ生きているか』(集英社)を刊行した。ひと口に作家といっても彼は漫画原作やノベライズ、ゲームやヴァーチャル楽曲とのコラボなども積極的にしていて、別にそちらが「副業」というわけではない。つまり小説と他ジャンルとの間の垣根が低い、というよりほとんど地続きにアーティスト同士が交流しているのである。名古屋市も、今後はそういう世代の文化に目を向けて振興を応援する必要があるだろう。
地域の文学に話題を戻そう。第37回中部ペンクラブ文学賞(以下、中ペン賞)の受賞者は、小森由美の「忘れ雪」だった。急病で母親を亡くした大学生の青年が、山形の母の実家へ心を休めに行き、雪に閉ざされた厳しい自然の中で縁者の優しさに触れて次第に立ち直る物語である。近親者の死を描く小説は数多く書かれているが、この小説はその欠落が若者の心をむしばむ経緯がじつに繊細に描かれている。それが昔戦争で兄を失った曽祖母の体験談とも連動して、世代を超えたスケールの大きな死の受容のテーマを浮かび上がらせている。小森の最新作「爪を切る音」(『弦』116号)も、夫に先立たれた女性が葬儀社の司会の仕事で、たまたま30年前に知り合った男と再会し、交際を始める作品である。喪失を抱えた熟年の心の機敏を掬い取る手腕は変わらず鮮やかだ。
他の同人雑誌掲載の小説では、北川朱実の「深夜保健室」(『文芸中部』126号)を挙げたい。北川は詩人として活躍中だが、小説も達者である。都会の繁華街に開業した個人経営の薬局の女性店主が、底辺で働く若者たちの愚痴や悩みに耳を傾け、ときには食事を振舞い、ジャズの名曲とプレイヤーの人生を語って聞かせる。そんな交流が薬局を雑踏の中の小さなオアシスにしていく物語である。
なお最近のニュースとして、中ペン賞の2017年受賞者である山口馨が、受賞作「駑馬」を含む作品集『砂の本』(鳥影社)を刊行したことを紹介しておく。地方でコツコツと純度の高い小説を書き続けた努力の結実である。

『推しはまだ生きているか』/集英社
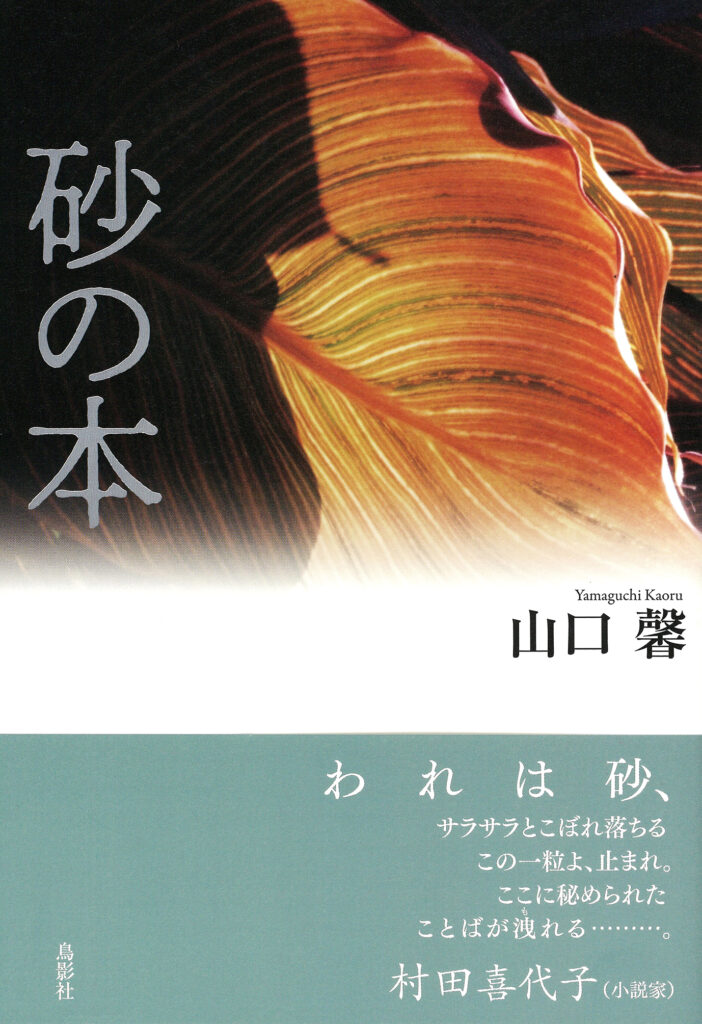
装幀・装画 毛利一枝